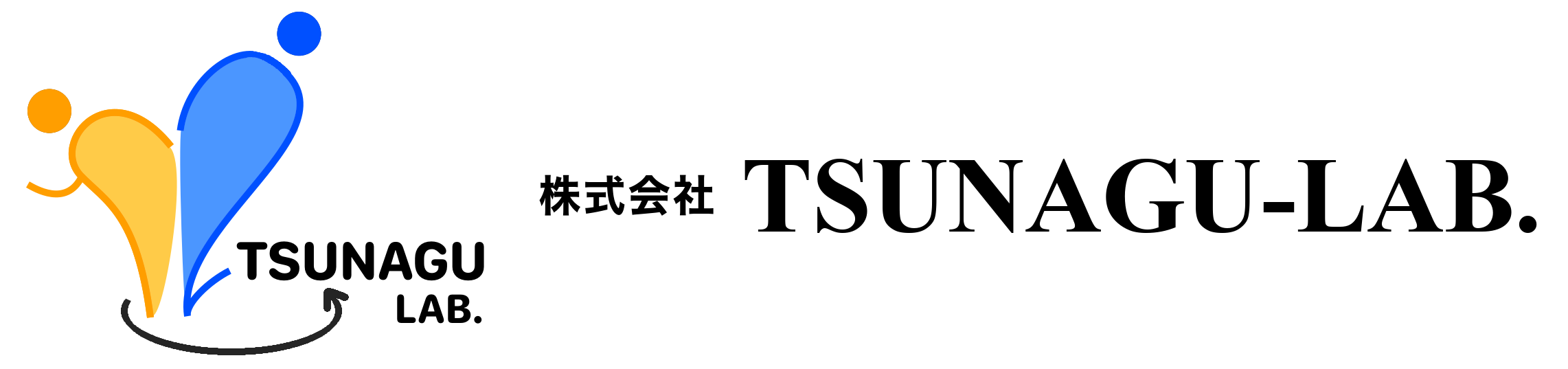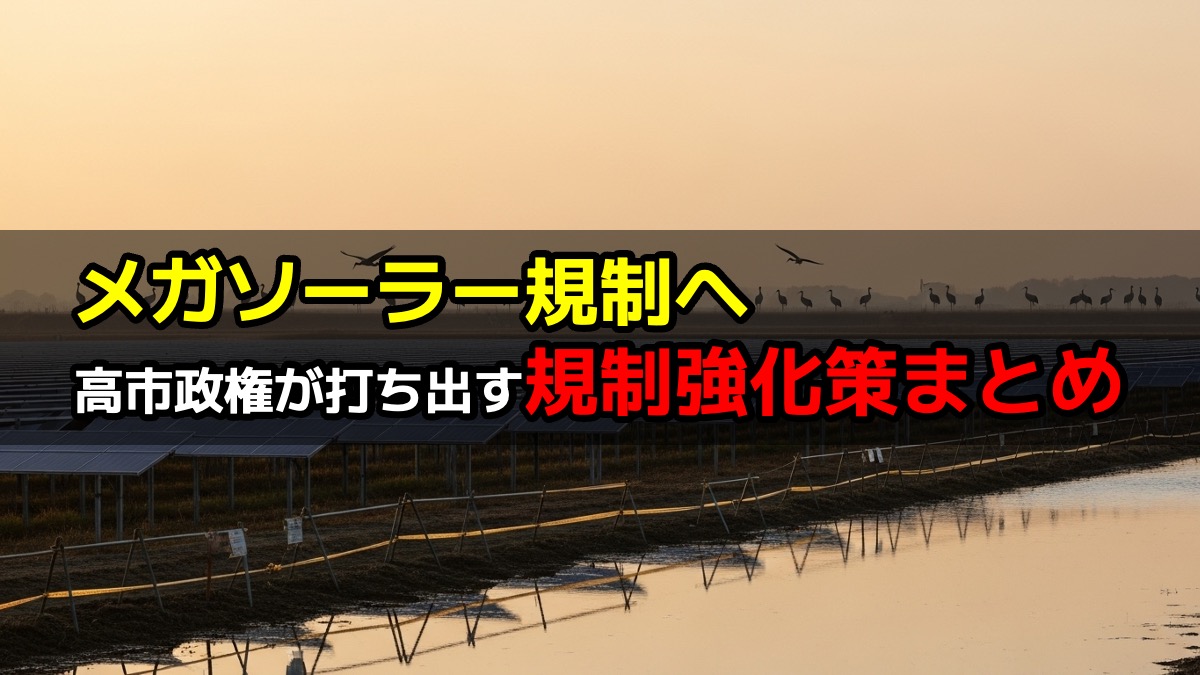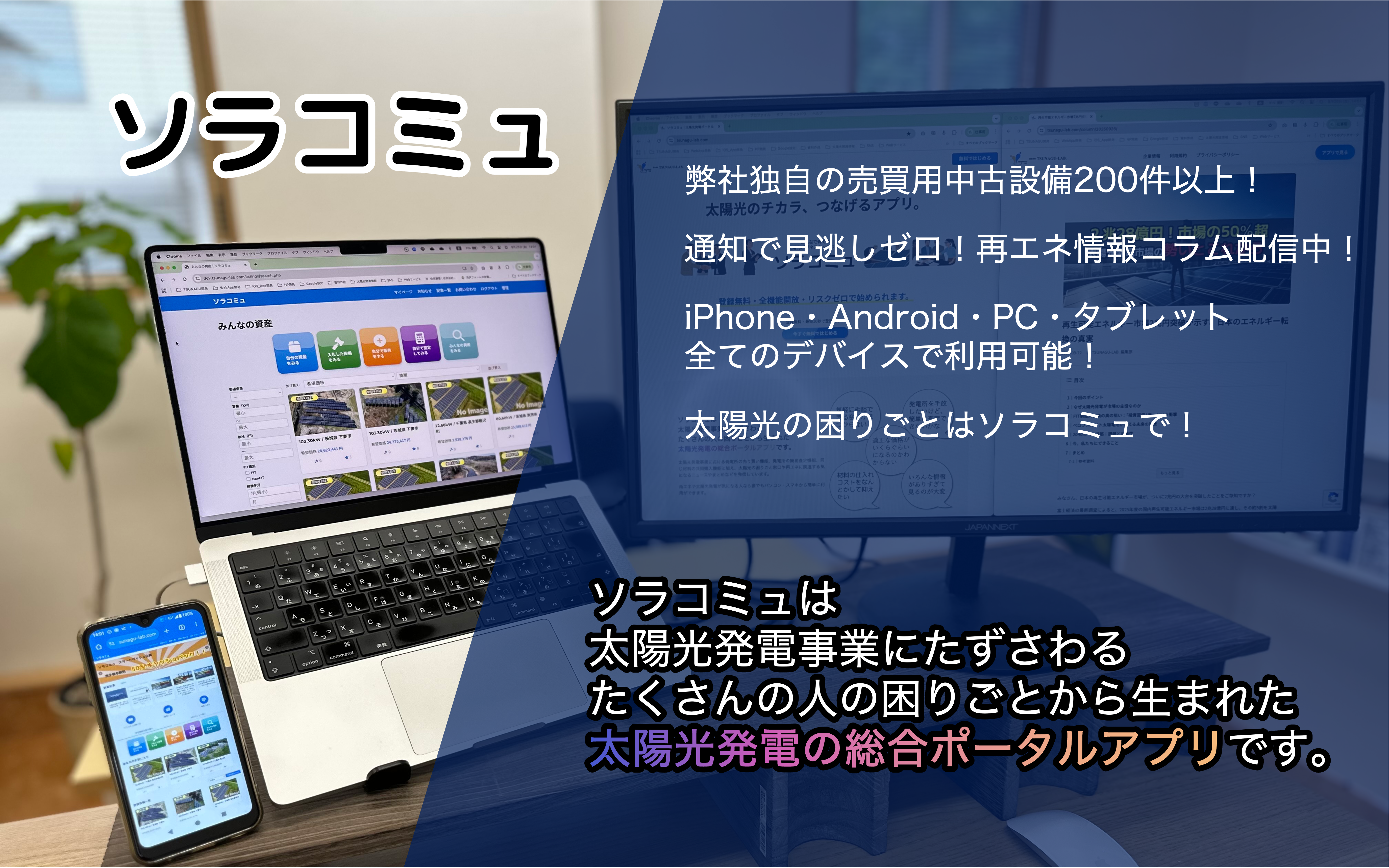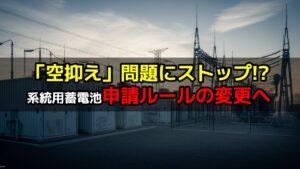「外国製パネルで国土を埋め尽くすことに猛反対」- 高市政権が打ち出した歴史的方針転換
2025年10月22日、高市早苗政権が本格始動し、日本のエネルギー政策に大きな転換点が訪れました。高市首相は9月19日の自民党総裁選出馬会見で「私たちの美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすことには猛反対だ」と明言し(出典:産経新聞 2025年10月25日)、メガソーラーの法的規制強化に本格的に乗り出す姿勢を鮮明にしました。
さらに9月22日の総裁選演説会では、「釧路湿原に太陽光パネルを敷き詰めるようなやり方はおかしい。補助金制度の大掃除をして本当に役に立つものに絞り込む」と述べ(出典:日本経済新聞 2025年9月22日)、これまでの太陽光発電偏重政策から大きく舵を切る意向を表明しています。
無秩序な開発の実態 – FIT制度導入から13年、全国323自治体が独自条例で対抗
2012年度に固定価格買取制度(FIT)が導入されて以降、太陽光発電施設は全国で急激に増加しました。地方自治研究機構によると、2025年6月末時点で全国323自治体がメガソーラー規制条例を制定しています(出典:産経新聞 2025年10月25日)。
条例制定は2016年以降、毎年2桁に上っており、全国に先駆けて2014年に条例を制定した大分県由布市の担当者は「自然豊かな景観の中で広範囲に人工物が見えることを危惧した」と説明しています(前掲産経新聞)。しかし、地域の対応の指針となる国の法整備が追いついておらず、無秩序な開発に歯止めがかかっていない状況が続いてきました。
高市政権が打ち出す具体的な規制強化策
高市政権は、以下の具体的な施策を通じてメガソーラー規制を強化する方針です:
1. 環境副大臣に青山繁晴氏を起用
太陽光パネルの廃棄問題など再エネの「負の部分」を訴えてきた青山繁晴氏を環境副大臣に起用し、規制強化の姿勢を人事面でも明確にしました(出典:産経新聞 2025年10月25日)。
2. 連立政権合意に規制実行を明記
自民党と日本維新の会は10月20日に交わした連立政権合意書で「わが国に優位性のある再生可能エネルギーの開発を推進する」とし、地熱発電の推進を明記しました(前掲産経新聞)。
3. 「悪い太陽光」の明確な規制
石原宏高環境相は就任記者会見で「自然破壊、土砂崩れにつながる『悪い太陽光』は規制していかなくてはいけない」と述べています(出典:はっさーブログ 2025年10月26日)。
4. 関係省庁連絡会議の発足
政府は2025年9月24日に関係省庁連絡会議を発足させ、環境省、国土交通省、経済産業省資源エネルギー庁など7省庁が連携して規制強化へ本格始動しました(出典:東京新聞デジタル 2025年9月28日)。
釧路湿原問題が象徴する環境と再エネの対立
高市首相の発言の背景には、釧路湿原で起きているメガソーラー問題があります。国の特別天然記念物タンチョウの生息地である釧路湿原周辺で、大阪の事業者「日本エコロジー」がメガソーラー建設を進めており、環境省釧路湿原野生生物保護センターからわずか300メートルの場所で6,600枚のソーラーパネル設置が計画されています(出典:HBC北海道放送)。
釧路市は10月1日、全国最先端とされる規制条例を施行しました。鶴間秀典市長は「今回作った条例は全国的にも最先端。自然と調和していない太陽光発電を増やさないために、力を合わせていきたい」と述べています(出典:UHB北海道文化放送 2025年10月1日)。
この問題に対し、Change.orgでの署名活動には7万3,000筆が集まり、モデルの冨永愛氏も「なんで貴重な生態系のある釧路湿原にメガソーラー建設しなきゃならないのか」とX(旧Twitter)で疑問を投げかけるなど、社会的関心が高まっています(出典:peckersの野鳥ブログ 2025年7月4日)。
土砂災害リスクの増大 – 全国で相次ぐ崩落事例
メガソーラー設置と土砂災害の関連性も大きな課題となっています。2020年10月には埼玉県嵐山町でメガソーラーが建設された土地の斜面が崩れ、2017年には千葉県匝瑳市でもソーラーシェアリング実施場所で地盤崩落が発生しました(出典:最安値発掘隊コラム 2022年9月17日)。
森林伐採による保水力の低下が土砂災害リスクを高める可能性が指摘されており、気候変動により豪雨災害が激甚化する中、新たな災害リスクとして認識されています。
専門家の見解 – 規制の必要性と課題
法政大学の茅野恒秀教授(地域環境政策専門)は「メガソーラーだけ規制する法的根拠が十分ではない」と指摘し、「太陽光発電に限らず、蓄電所やほかのエネルギーでも設置による地域とのトラブルは起こりうる」と公平性の問題を提起しています(出典:産経新聞 2025年10月25日)。
一方、ジャーナリストの鈴木哲夫氏は「メガソーラーで問題が起きても対処法を考えればいい。再エネ批判で『原発しかない』という空気感を醸成しようとしている」と、政治的な意図を指摘しています(出典:東京新聞デジタル 2025年9月28日)。
ペロブスカイト太陽電池への期待 – 日本発技術による解決策
赤沢亮正経済産業相は、規制強化だけでなく「次世代型太陽光発電の開発や導入を支援する」と語り、薄くて軽く曲げられるペロブスカイト太陽電池の開発支援を表明しました(出典:時事ドットコム 2025年10月24日)。
積水化学工業は2025年の事業化、2027年に100MW製造ライン稼働を発表しており、政府は2040年までに20GWの導入目標を設定しています(出典:省エネの教科書 2025年10月7日)。この日本発の技術により、従来設置できなかった場所への展開が可能になり、メガソーラーの代替手段として期待されています。
電力安定供給とのバランス – 高市政権の新たなアプローチ
高市首相は「再エネの比重を上げすぎると電力の安定供給が難しくなる」との見解を示し(出典:はっさーブログ 2025年10月26日)、火力発電や原子力発電とのバランスを重視する姿勢を明確にしています。
これは、2030年の再エネ比率目標36-38%の達成方法を根本的に見直す可能性を示唆しており、脱炭素と電力安定供給の両立という難題に対する新たなアプローチとして注目されています。
国民負担の実態 – 年間約2万円の隠れたコスト
2025年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金は1kWh当たり3.98円で、月400kWh使用の標準家庭では年額19,104円の負担となっています(出典:リアルタイムニュース.com 2025年9月22日)。この「隠れた家計負担」も、高市首相が補助金制度の見直しを主張する背景にあります。
まとめ – エネルギー政策の歴史的転換点
高市政権のメガソーラー規制強化は、2012年のFIT制度導入以来の太陽光発電偏重政策からの大きな転換を意味します。全国323自治体が独自条例で対応してきた問題に、ついに国が統一基準を示す方向へ動き出しました。
釧路湿原問題に象徴される環境保護と再生可能エネルギー推進の対立、土砂災害リスクの増大、国民負担の増加など、複合的な課題に直面する中、高市政権は「わが国に優位性のある再エネ開発」という新たな方向性を打ち出しています。
ペロブスカイト太陽電池など日本発の技術開発を推進しながら、「悪い太陽光」を規制し、電力の安定供給とのバランスを取る―この難しい舵取りが成功するかどうかは、日本のエネルギー安全保障と環境保護の両立にとって極めて重要な試金石となるでしょう。
参考文献
- 産経新聞「無秩序メガソーラー 『猛反対』の高市首相が規制強化方針 外国製パネルが国土埋め尽くし」(2025年10月25日)
- 日本経済新聞「高市早苗氏、太陽光発電など『補助金制度を大掃除』自民党総裁選演説会」(2025年9月22日)
- 東京新聞デジタル「釧路メガソーラーが起こした波紋…規制と推進、最適なバランスは」(2025年9月28日)
- UHB北海道文化放送「【釧路湿原メガソーラー問題】市が求めていた特別天然記念物『タンチョウ』の再調査結果を事業者が提出」(2025年10月1日)
- 時事ドットコム「メガソーラーへの規制強化 『ペロブスカイト』導入支援も―赤沢経産相・新閣僚インタビュー」(2025年10月24日)
- 省エネの教科書「【2025年最新動向】ペロブスカイト太陽電池の基礎知識と市場流通」(2025年10月7日)
※この記事はWriters-hub様のご協力によりAIで生成・編集した記事を元に作成しました。
記事内容の詳細については参考資料をご覧ください。