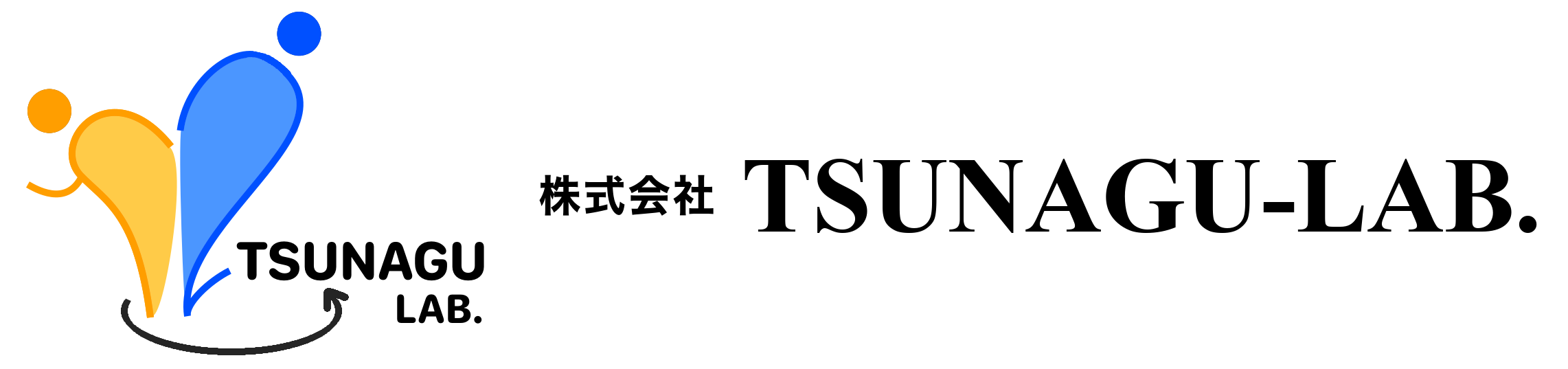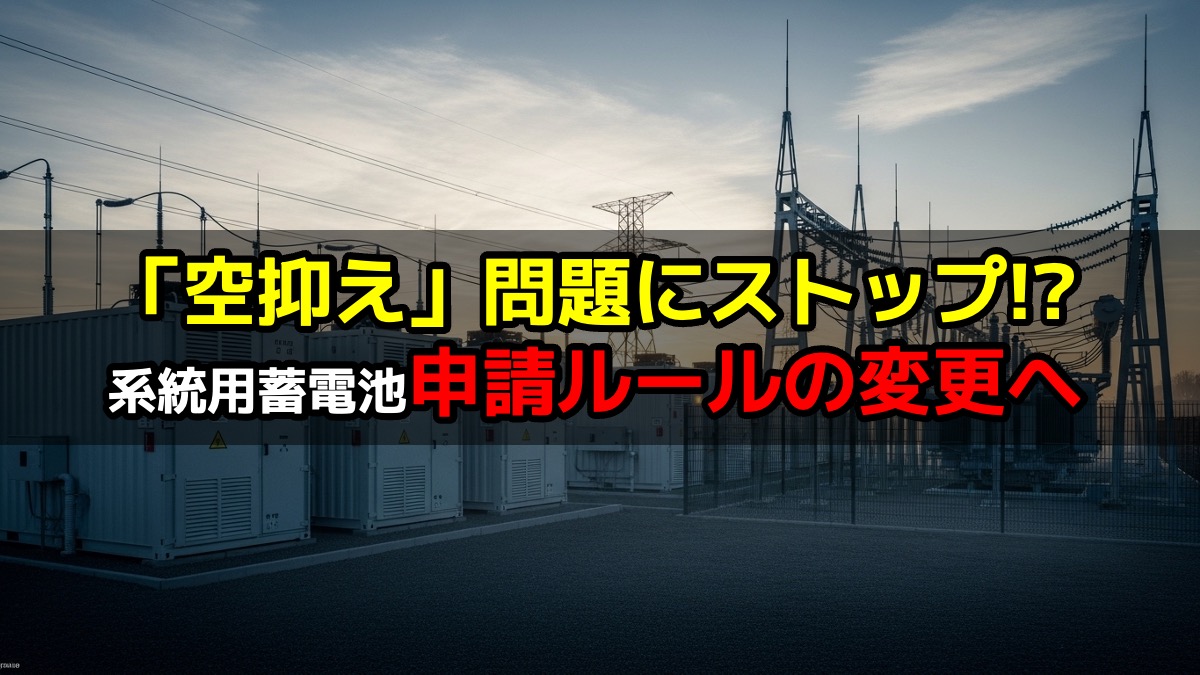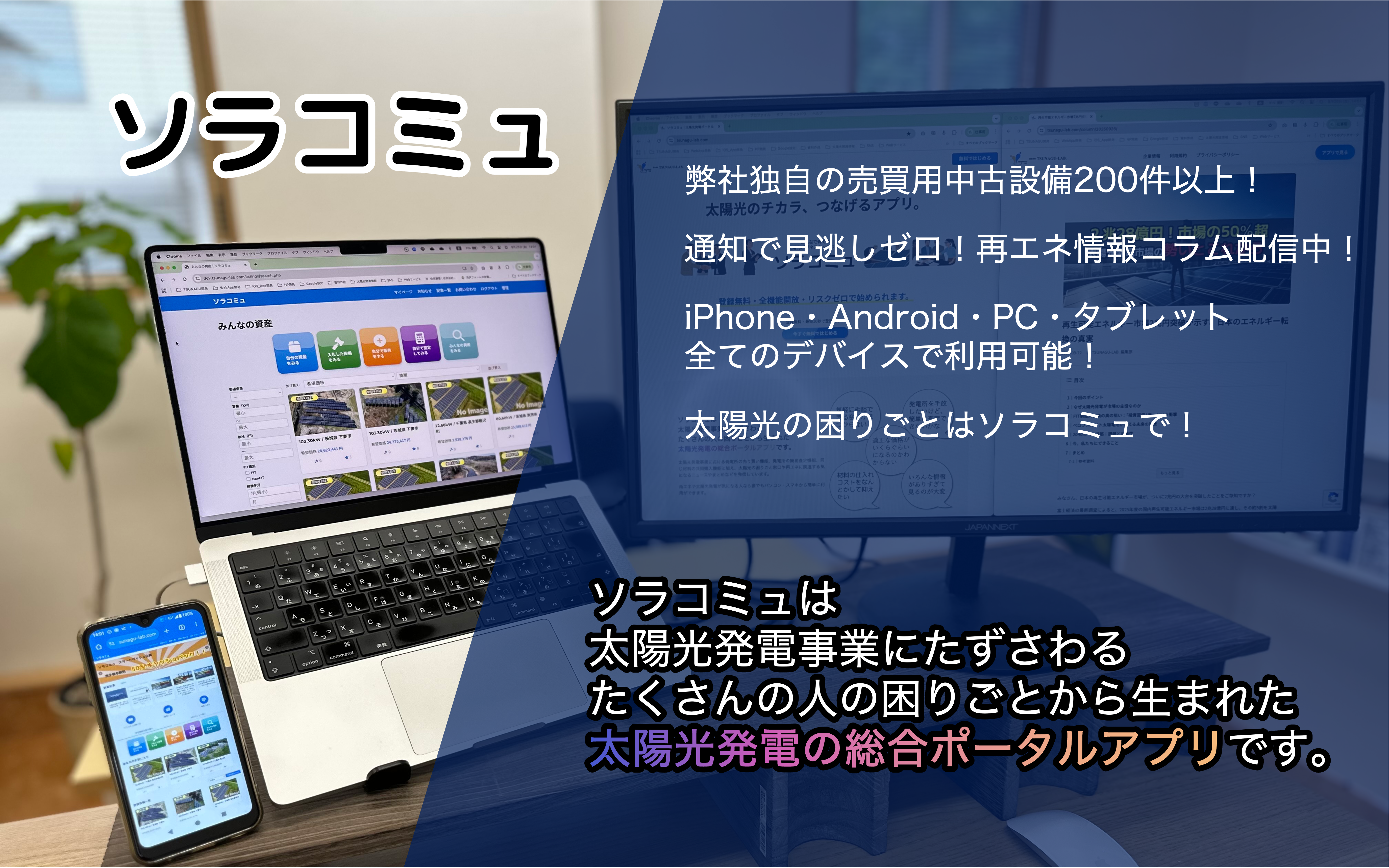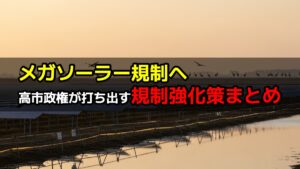読了時間 約8分
1.1億kWの申請に対して実際の連系はわずか17万kW?
皆さん、再生可能エネルギーの普及に欠かせない「系統用蓄電池」の接続申請が、実に1億1300万kWに達していることをご存じでしょうか。これは日本の総発電設備容量の半分に迫る規模です。しかし驚くことに、実際に送電網に接続されている容量はわずか17万kW程度に過ぎません(出典:系統用蓄電池の接続検討が急増 受付量は1.1億kW超で「空押さえ」が課題に)。
この圧倒的なギャップこそが、今、日本のエネルギー転換を阻む「空押さえ」問題の実態なのです。経済産業省は2025年10月13日、この問題に対して2026年度から接続ルールを厳格化する方針を発表しました(出典:送電線「空押さえ」に待った 系統用蓄電池の接続申請に上限、実現性重視)。
空押さえの実態:51件もの申請を行う事業者も
経産省の調査によると、系統用蓄電池の1申請あたりの接続検討申し込み件数は、通常1~2件がボリュームゾーンとなっています。補助金申請の場合は約5割、オークションの場合は6割超が、このような適正な申請を行っています。
しかし一方で、1申請あたり10件以上の接続検討申し込みを行う事業者が約1割も存在し、なかには51~55件もの申し込みを行うケースまで報告されています(出典:系統用蓄電池の「空押さえ」、経産省が対策へ)。
これは明らかに異常な状況です。一部の事業者が実現性の乏しい計画で送電網の接続枠を大量に確保し、本当に必要としている事業者やデータセンターなどの接続を妨げているのです。
なぜ空押さえが起きたのか:制度設計の盲点
では、なぜこのような事態が発生したのでしょうか。実は、この問題の背景には複数の要因が絡み合っています。
1. 補助金・オークション制度の副作用
系統用蓄電池への投資を促進するため、政府は補助金制度や長期脱炭素電源オークションを実施してきました。しかし、これらの制度を利用するためには、事前に電力会社からの「接続検討回答書」が必要となります(出典:系統用蓄電池ビジネスが過熱!「空押さえ」問題と今後の新ルールを徹底解説)。
このため、補助金やオークションの締め切り前に、とりあえず大量の接続検討を申し込むという行動が横行しました。いわば「念のため」の申請が、システム全体を圧迫する結果となったのです。
2. 投機的な動きの存在
さらに深刻なのは、接続権を転売目的で取得する投機的な動きも報告されていることです(出典:蓄電池市場急拡大の『光と影』〜再エネ事業者が知るべき業界構造変化)。蓄電池事業自体を行う意図はなく、権利だけを確保して転売利益を狙う事業者が参入しているのです。
3. 充電と放電の複雑な制御問題
系統用蓄電池は、放電時(逆潮流)だけでなく充電時(順潮流)においても系統への影響を考慮する必要があります。特に充電時は、データセンターなど他の大口需要家と競合することになり、系統増強が必要となるケースが多発しています(出典:系統用蓄電池の連系が進まない理由と2025年4月開始の追加対策の内容をわかりやすく紹介)。
経産省の対策:規制強化の狙いと影響
こうした状況を受けて、経産省は2026年度から以下の対策を実施する方針です。
申請数への上限設定
送配電会社への申請数に上限を設け、むやみな大量申請を防ぎます。
調査資料の提出義務化
設置場所の調査資料の提出を求めることで、実現性の低い計画を事前にスクリーニングします。
ノンファーム型接続の拡大検討
充電側でも系統混雑時の制御を前提としたノンファーム型接続の導入を検討し、限られた系統容量をより効率的に活用する方向性も示されています(出典:エネ庁、系統蓄電池接続ルール見直しへ/空押さえ、投機防止)。
見落とされがちな視点:データセンター需要との競合
実は、この空押さえ問題には、もう一つの重要な側面があります。それは、急増するデータセンターの電力需要との競合です。
生成AIの普及により、データセンターの電力需要は2034年度には2025年度比で約13倍になると予測されています(出典:今後の電力需要の見通しについて)。データセンターも蓄電池と同様に大量の電力を必要とし、送電網への接続を求めています。
つまり、空押さえ問題は単に蓄電池業界内の問題ではなく、日本のデジタル化と脱炭素化という二つの重要な国家戦略が、限られた送電インフラを巡って競合している構図なのです。
これからの展望:真の課題は送電網の抜本的強化
経産省の規制強化は確かに必要な対策ですが、それだけでは根本的な解決にはなりません。なぜなら、問題の本質は「送電網のキャパシティ不足」にあるからです。
政府は今後10年間で、過去10年の8倍規模となる1000万kW以上の地域間連系線整備を計画しています(出典:電力ネットワークの次世代化について)。しかし、これでも急増する蓄電池とデータセンターの需要を賄えるかは未知数です。
まとめ:今こそ必要な3つのアクション
空押さえ問題から見えてきたのは、日本のエネルギー転換が重要な岐路に立っているという事実です。再エネの主力電源化を実現するためには、以下の3つのアクションが不可欠です。
1. 事業者の意識改革
蓄電池事業に参入する事業者は、短期的な利益追求ではなく、エネルギーシステム全体への貢献を意識した事業計画を立てる必要があります。
2. 制度設計の見直し
補助金やオークション制度は、真に実現性の高い事業を優先的に支援する仕組みへと進化させる必要があります。申請時点での事業計画の精査をより厳格化することも検討すべきでしょう。
3. 送電インフラへの大胆な投資
最も重要なのは、送電網への大胆な投資です。再エネとデジタル化の両立を図るためには、現在の計画を上回る規模での送電網強化が必要となるでしょう。
空押さえ問題は、単なる規制の問題ではありません。それは、日本が脱炭素社会への転換をどれだけ本気で進めるかという、私たち全体への問いかけなのです。
参考資料
- スマートジャパン(ITmedia)「系統用蓄電池の接続検討が急増 受付量は1.1億kW超で「空押さえ」が課題に」(2025年7月2日)
- 日本経済新聞「送電線「空押さえ」に待った 系統用蓄電池の接続申請に上限、実現性重視」(2025年10月13日)
- 日経BP メガソーラービジネス「系統用蓄電池の「空押さえ」、経産省が対策へ」(2025年7月3日)
- 環境エネルギー情報局「系統用蓄電池の連系が進まない理由と2025年4月開始の追加対策の内容をわかりやすく紹介」
- 情熱電力「系統用蓄電池ビジネスが過熱!「空押さえ」問題と今後の新ルールを徹底解説」(2025年7月18日)
- 電気新聞「エネ庁、系統蓄電池接続ルール見直しへ/空押さえ、投機防止」(2025年6月28日)
- note「蓄電池市場急拡大の『光と影』〜再エネ事業者が知るべき業界構造変化」(2025年7月4日)
- 資源エネルギー庁「今後の電力需要の見通しについて」(2025年1月27日)
- 資源エネルギー庁「電力ネットワークの次世代化について」(2025年6月3日)
- 資源エネルギー庁「系統用蓄電池の現状と課題」(2024年5月29日)
※この記事はWriters-hub様のご協力によりAIで生成・編集した記事を元に作成しました。
記事内容の詳細については参考資料をご覧ください。