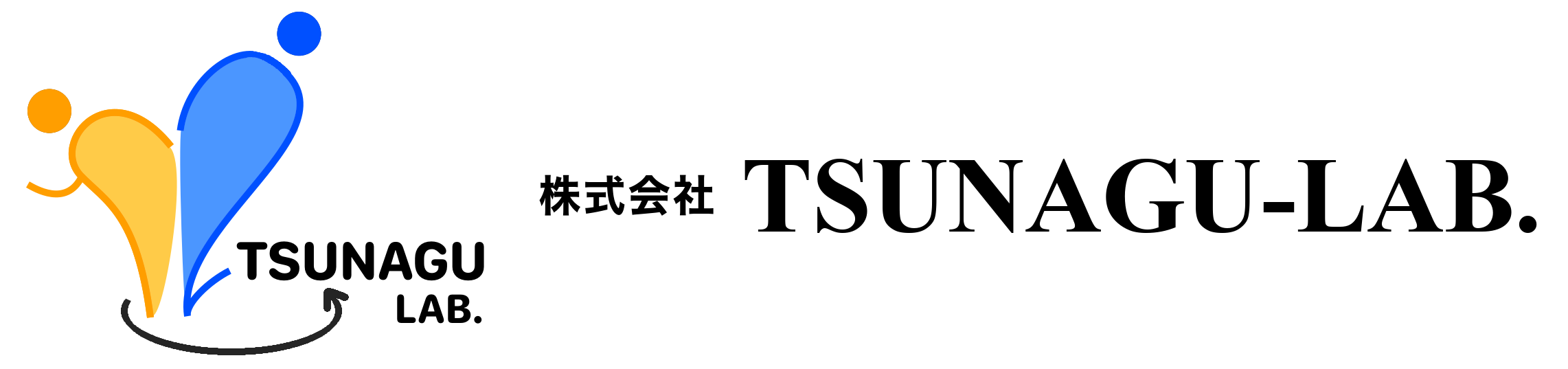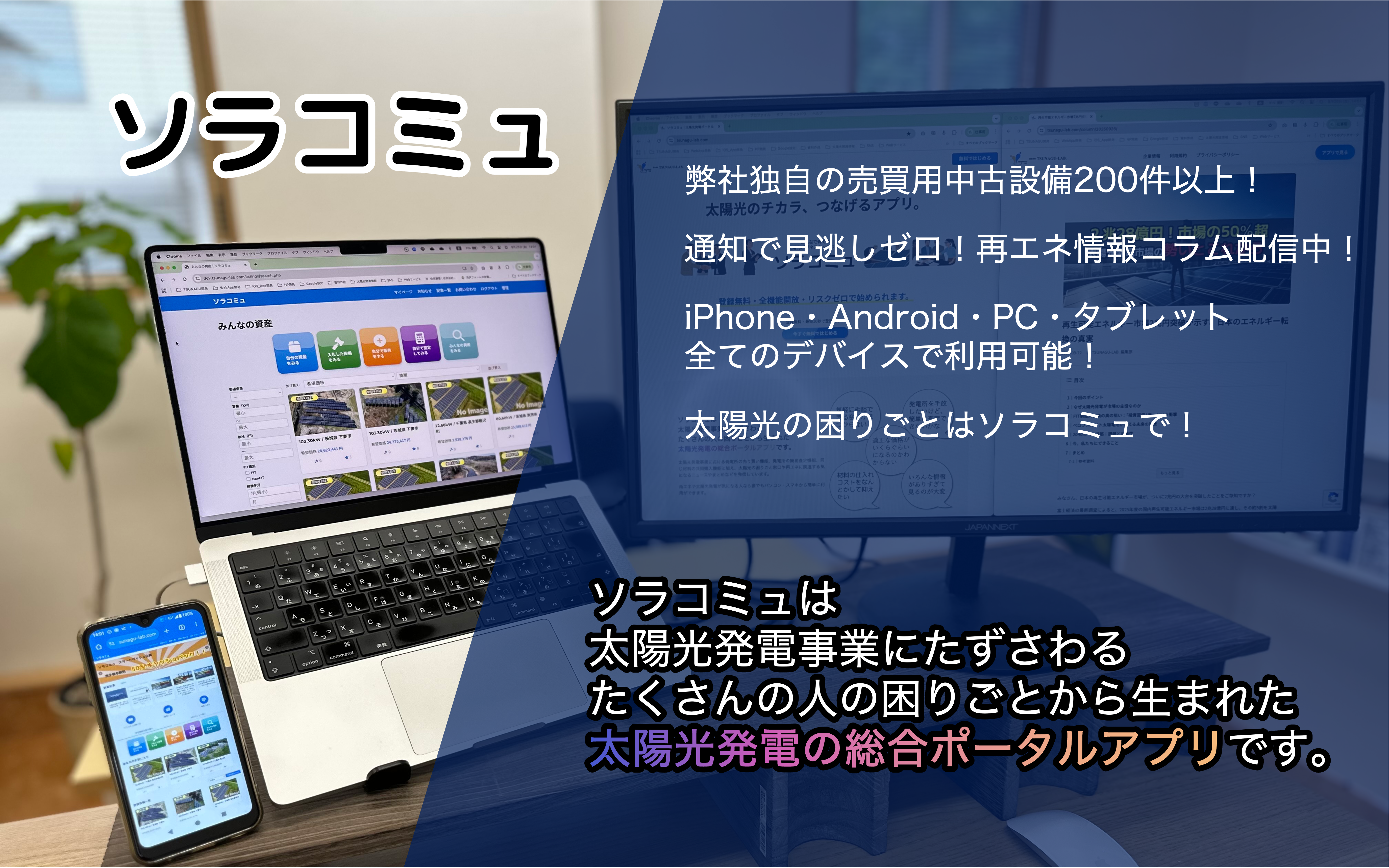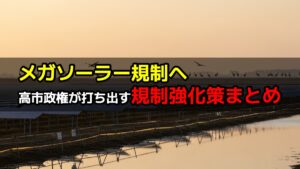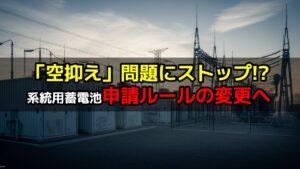(読了時間8分)
2025年11月、英誌『The Economist』が報じた中国の再生可能エネルギー革命の実態は、世界に衝撃を与えています。「人間が想像もできないほどのすさまじい規模」という表現は決して大げさではありません。2024年末までに設置された太陽光発電容量887ギガワット(GW)は、欧州と米国の合計の2倍近くに達し、年間で原発300基分に相当する再生可能エネルギーを追加するという、前例のない速度で転換が進んでいるのです(出典:日本経済新聞「中国再エネ、温暖化から世界を救うか」 2025年11月11日)。
果たして、この中国の再エネ革命は、本当に世界を温暖化から救う希望となるのでしょうか。それとも新たな地政学的リスクを生み出すのでしょうか。
数字が語る「別次元」の成長速度
2025年前半だけで、中国が導入した風力・太陽光発電の規模は264GWに達しました。これは前年同期比で2倍という驚異的な加速です(出典:日経テックフォーサイト「編集者の視点『中国の再エネ導入量が前年同期比2倍に』」 2025年11月10日)。
この数字を日本と比較すると、その規模の違いがより鮮明になります。日本の太陽光発電の年間導入量は約5GW程度。つまり中国は半年で、日本の50年分以上の太陽光発電設備を導入したことになります。中国が2024年に風力タービンや太陽光パネルの生産に使った鋼材2200万トンは、平日毎日サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ1本分に相当するという比喩も、その規模の巨大さを物語っています。
さらに衝撃的なのは、この成長がまだ加速し続けていることです。2022年末時点で中国の自然エネルギー発電設備容量は1,213GWに達し、史上初めて石炭火力発電の1,120GWを超えました(出典:自然エネルギー財団「中国における電力部門の低炭素化の動向」 2023年11月6日)。2025年には風力と太陽光を合わせた発電能力が火力発電を完全に上回る見込みで、エネルギー史における歴史的な転換点を迎えつつあります。
世界のサプライチェーンを支配する「グリーン製造大国」
中国の再エネ革命を支えているのは、圧倒的な製造能力です。国際エネルギー機関(IEA)の報告によれば、太陽光パネルの主要製造段階での中国のシェアは8割を超え、ポリシリコンやウエハーについては今後数年で95%に達すると予測されています(出典:日本経済新聞「中国、太陽光パネルの製造過程でシェア8割 IEA報告」 2022年7月7日)。
Bloomberg NEFの分析では、太陽光発電と蓄電池関連の製造能力で中国はほぼ9割、風力発電でも3分の2のシェアを占めています。「中国が緑のサプライチェーンを支配」というコメントは、もはや誇張ではなく現実となっています(出典:サステナブル・ブランド ジャパン「脱炭素特集 世界の脱炭素技術を席巻する中国」 2024年)。
この製造能力の背景には、莫大な投資があります。中国は2011年以降、欧州の10倍以上に当たる500億ドル(約6兆8000億円)を太陽光パネル産業に投資し、30万人の雇用を創出しました。その結果、太陽光パネルの価格は2010年から2025年にかけて97%以上下落し、世界中での普及を可能にしました。
矛盾を抱えた転換:再エネ拡大と石炭火力の二面性
しかし、中国のエネルギー転換は単純な成功物語ではありません。注目すべきは、再生可能エネルギーの大規模導入と同時に、石炭火力発電の新設も続いているという矛盾です。
中国政府は2025年に電力部門のCO2排出ピークアウトを目標に掲げながら、「次世代の石炭火力発電のグレードアップ特定行動実施方案(2025-2027年)」を発表し、2027年まで石炭火力の新設を継続する方針を示しています(出典:JOGMEC「中国:国家発展改革委員会、国家能源局は『次世代の石炭火力発電のグレードアップ特定行動実施方案』を通達」 2025年4月)。
この「二面性」は、中国が直面するエネルギー安全保障と脱炭素の間のジレンマを反映しています。再生可能エネルギーの出力変動に対応するため、石炭火力を「バックアップ電源」として位置づけ、電力の安定供給を確保しようとしているのです。
COP29で見せた「気候リーダーシップ」への野心
2024年11月のCOP29では、中国の存在感が際立ちました。アゼルバイジャンで巨大な太陽光発電所建設への協力を発表し、開催国との連携を深めています(出典:日本経済新聞「COP29、中国が脱炭素で存在感」 2024年11月20日)。
特に注目すべきは、トランプ政権のパリ協定離脱決定後の中国の動きです。途上国向けの気候資金供与で中国が大きな役割を果たす意向を示し、「南南協力」という枠組みで、自国で生産された再エネ設備や送電インフラを積極的に途上国に輸出する戦略を描いています(出典:MRI三菱総合研究所「2025年、世界の気候変動対策はどこへ向かうのか」 2025年1月)。
中国の戦略は明確です。世界最大の再エネ製造能力と、年間300兆円規模とも言われる投資力を武器に、気候変動対策の国際的リーダーシップを握ろうとしているのです。
世界にとってのチャンスとリスク
中国の再エネ革命は、世界にとって大きなチャンスであると同時に、新たなリスクも生み出しています。
チャンスとしては、太陽光パネルの劇的な価格低下により、世界中で再生可能エネルギーの導入が加速していることが挙げられます。中国の大量生産により、太陽光発電は多くの地域で最も安い発電技術の一つとなりました。
一方でリスクも無視できません。サプライチェーンの中国への過度な集中は、地政学的な脆弱性を生み出しています。新疆ウイグル自治区にポリシリコン生産の42%が集中している現状は、人権問題と供給安定性の両面から懸念されています。
米国やEUは関税強化や国内生産促進策で対応を始めていますが、中国の圧倒的な価格競争力の前では限定的な効果にとどまっています。
まとめ:「想像を超える規模」が変える世界
The Economistが描いた中国の再エネ革命は、確かに「想像を超える規模」で進行しています。年間で原発300基分の再エネを追加し、世界の太陽光パネル製造の8割を支配する中国は、好むと好まざるとにかかわらず、世界の脱炭素化の鍵を握る存在となりました。
しかし、この革命が「世界を救う」かどうかは、まだ分かりません。石炭火力との二面性、サプライチェーンの集中リスク、地政学的な対立など、多くの課題が残されています。
確実なのは、中国の再エネ革命が世界のエネルギー地図を根本から塗り替えつつあるということです。私たちは今、エネルギー史における大転換の真っただ中にいます。この変化にどう向き合い、どう活用していくか。それが問われているのです。
参考資料
- 日本経済新聞「中国再エネ、温暖化から世界を救うか(The Economist)」(2025年11月11日)
- 日経テックフォーサイト「編集者の視点『中国の再エネ導入量が前年同期比2倍に』」(2025年11月10日)
- 風傳媒日本語版「中国が『クリーンエネルギー超大国』へ」(2025年11月)
- 自然エネルギー財団「中国における電力部門の低炭素化の動向」(2023年11月6日)
- 日本経済新聞「COP29、中国が脱炭素で存在感」(2024年11月20日)
- 日本経済新聞「中国、太陽光パネルの製造過程でシェア8割 IEA報告」(2022年7月7日)
- サステナブル・ブランド ジャパン「世界の脱炭素技術を席巻する中国」(2024年)
※この記事はWriters-hub様のご協力によりAIで生成・編集した記事を元に作成しました。
記事内容の詳細については参考資料をご覧ください。