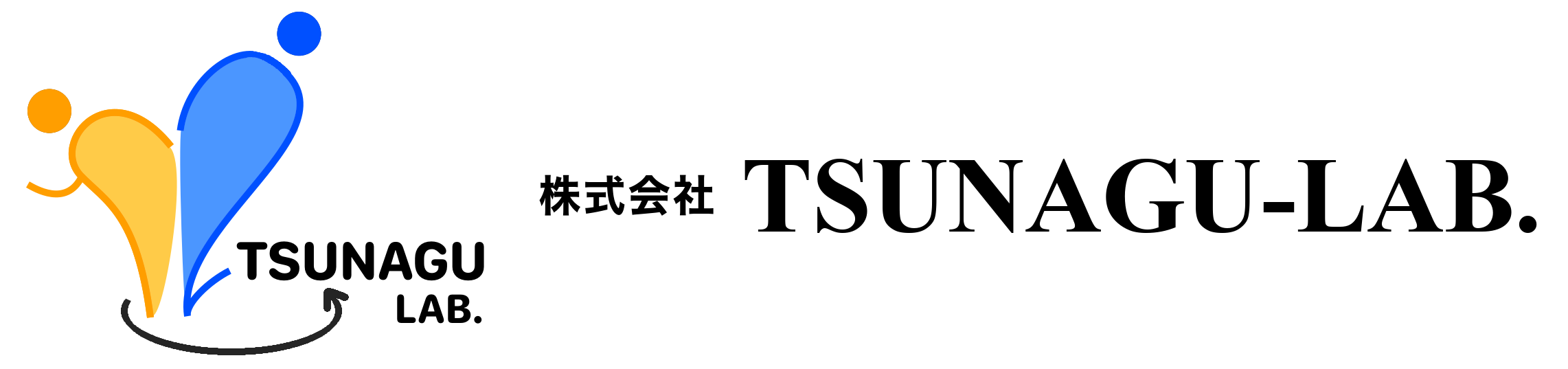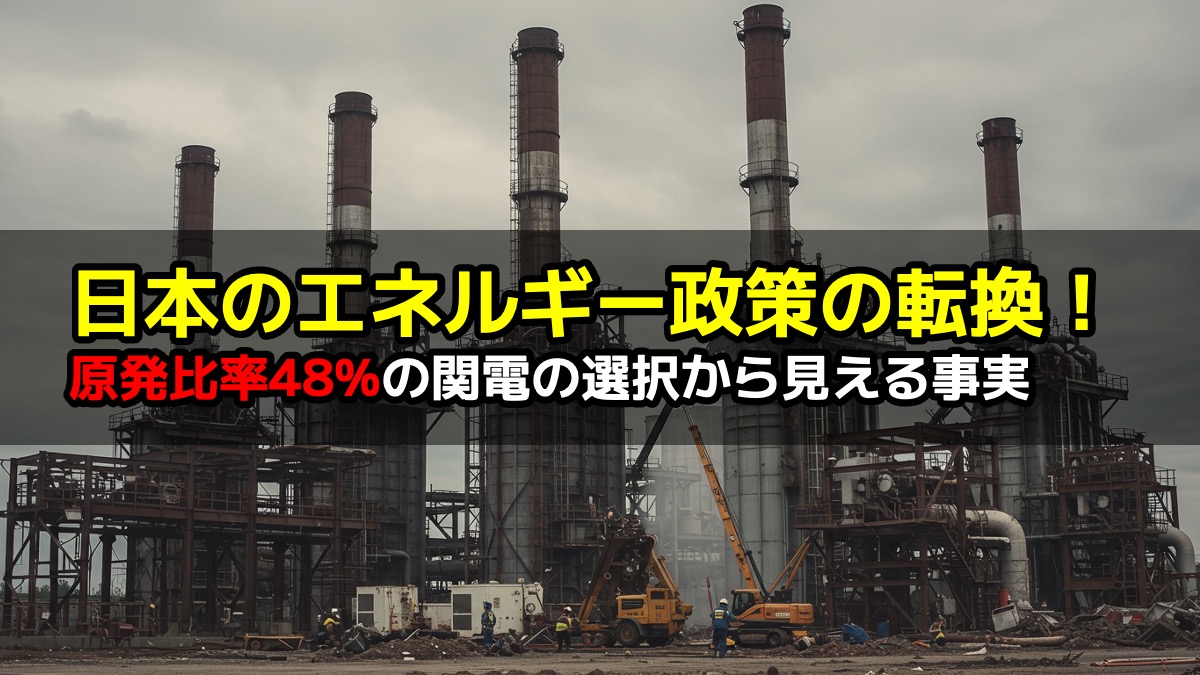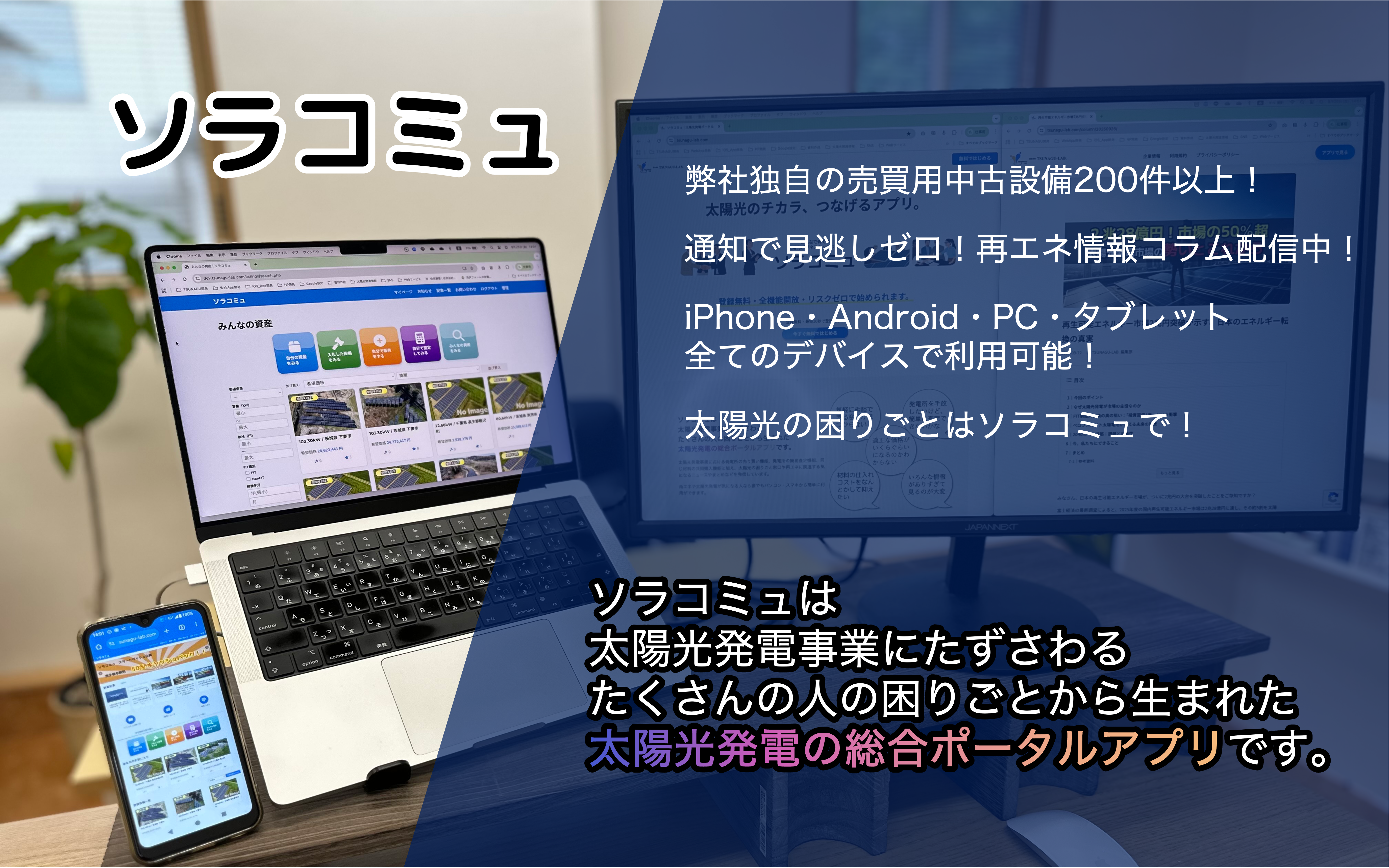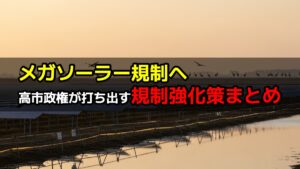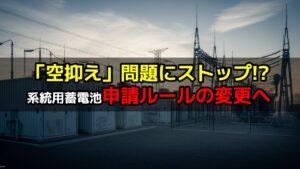読了時間:約8分
2025年9月26日、関西電力が御坊発電所1、2号機の廃止を正式発表しました。これは単なる老朽火力発電所の廃止という話ではありません。日本の電力会社として初めて、石油火力からの完全撤退へと大きく舵を切る歴史的な決断であり、日本のエネルギー政策転換の象徴的な事例となっています。
原発比率48%という異例の高さが示すもの
関西電力の電源構成を見ると、驚くべき数字が浮かび上がります。2024年度の原発比率は48%に達し、石油火力は0.1%未満まで減少しています(日本経済新聞 2025年9月26日)。
この数字がいかに異例かは、全国平均と比較すると明らかです。2024年の日本全体の原発比率は8.2%に過ぎません(ISEP環境エネルギー政策研究所 2025年7月10日)。つまり、関西電力は全国平均の約6倍もの原発依存度を持っているのです。
さらに驚くべきは、関西電力の原発設備利用率が2024年度に88.5%に達したことです(日本経済新聞 2025年4月3日)。美浜3号機、高浜1~4号機、大飯3・4号機の計7基がフル稼働体制に入り、東日本大震災以降で最高水準を記録しています。
なぜ今、石油火力を全面廃止するのか
御坊発電所は1984年に運転を開始し、日本で初めて外洋(太平洋)に造られた人工島方式の発電所として注目を集めました(Wikipedia 御坊発電所)。しかし、40年という長い歴史に幕を下ろす決断の背景には、複数の要因が重なっています。
第一に、経済的な理由があります。原発の再稼働が進んだことで、石油火力の稼働率は極めて低くなっていました。2号機は2019年4月から設備不具合で休止しており、実質的にはすでに戦力外でした(日高新報 2025年9月29日)。
第二に、脱炭素の圧力です。石油火力は液化天然ガス(LNG)と比較してもCO2排出量が多く、2050年カーボンニュートラル目標に向けて真っ先に廃止対象となる電源です。
しかし、最も注目すべきは第三の理由、つまり原発への戦略的シフトです。関西電力は単に石油火力を減らしているのではなく、明確に原発を主力電源として位置づけているのです。
地域経済への配慮と新技術への転換
御坊発電所の廃止は、地域経済に大きな影響を与えます。約80人の従業員は廃止後に約50人となり、30人の雇用が失われます(日本経済新聞 2025年9月26日)。
しかし、関西電力は地域への配慮も忘れていません。代替となる地域活性化の取り組みとして、御坊市内への蓄電所建設を検討しています。建設場所は市街地を視野に入れており、旭化成和歌山工場跡地(約2ヘクタール)も候補地になる可能性があります(日高新報 2025年9月29日)。
これは単なる雇用対策ではありません。再生可能エネルギーの出力変動を吸収する蓄電所は、今後のエネルギーシステムにおいて重要な役割を果たします。古い火力発電所を新しいエネルギーインフラに置き換える、まさに時代の転換を象徴する動きと言えるでしょう。
日本のエネルギー政策の大転換
関西電力の動きは、日本のエネルギー政策全体の転換と軌を一にしています。2024年12月に発表された第7次エネルギー基本計画の原案では、福島原発事故以降続いてきた「原発依存度を可能な限り低減する」という文言が初めて削除されました(日本経済新聞 2025年1月21日)。
この変化の背景には、AI・データセンター需要の急増があります。ビッグテックが安価で安定的な脱炭素電源を求める中、原発の価値が再評価されているのです。実際、米国ではマイクロソフトがスリーマイル島原発の再稼働を決めるなど、世界的にも原発回帰の動きが加速しています。
電力料金への影響:原発稼働の経済効果
興味深いのは、原発稼働率と電力料金の関係です。原発が再稼働している関西電力、九州電力、四国電力では、原子力比率が20%を超えており、その結果として電力料金が相対的に安くなっています。
具体的には、東京電力と九州電力を比較すると、家庭向けで約10円/kWh、企業向けでも約10円/kWhの差があります(株式会社恒電社 2025年1月8日)。これは原発の有無が電力料金に直接的な影響を与えることを示す明確な証拠です。
残された課題と将来への問い
しかし、関西電力の戦略にも課題があります。再生可能エネルギーへの取り組みは極めて限定的で、太陽光発電は15カ所、風力は2カ所が稼働するだけです(環境金融研究機構 2023年12月19日)。原発に偏重した電源構成は、将来的なリスクを孕んでいます。
また、使用済み核燃料の処理問題は依然として解決していません。フランスへの搬出や中間貯蔵施設の建設など、一定の進展はありますが、根本的な解決には至っていないのが現状です。
まとめ:エネルギー転換の最前線で
関西電力の石油火力全面廃止は、日本のエネルギー転換の最前線で起きている劇的な変化を象徴しています。原発比率48%という異例の高さは、良くも悪くも日本のエネルギー政策の行き先を示す試金石となるでしょう。
地域経済への配慮を示しながら、蓄電所という新技術への転換を進める関西電力の姿勢は評価できます。しかし同時に、再生可能エネルギーへの取り組み不足や使用済み核燃料問題など、解決すべき課題も山積しています。
私たちは今、エネルギー転換の歴史的な岐路に立っています。関西電力の選択が正しかったのか、それは時間が証明することになるでしょう。しかし確実に言えるのは、もはや後戻りはできないということです。
参考資料
- 日本経済新聞「関西電力、石油火力を廃止 脱炭素へ原発シフト」(2025年9月25日)
- 日高新報「御坊火力発電所一部廃止 市街地への蓄電所建設等代替案検討へ」(2025年9月29日)
- 日本経済新聞「関西電力、2024年度の原発発電量15%増 東日本大震災後で最大」(2025年4月3日)
- ISEP環境エネルギー政策研究所「2024年(暦年)の自然エネルギー電力の割合(速報)」(2025年7月10日)
- 日本経済新聞「原発推進に大転換 『エネルギー基本計画』10のQ&A」(2025年1月21日)
- 株式会社恒電社「【電力会社の電源構成比は知っておくべき】電力会社比較」(2025年1月8日)
- 環境金融研究機構「関西電力。和歌山市での大規模ガス火力発電所計画の廃止決定」(2023年12月19日)
※この記事はWriters-hub様のご協力によりAIで生成・編集した記事を元に作成しました。
記事内容の詳細については参考資料をご覧ください。