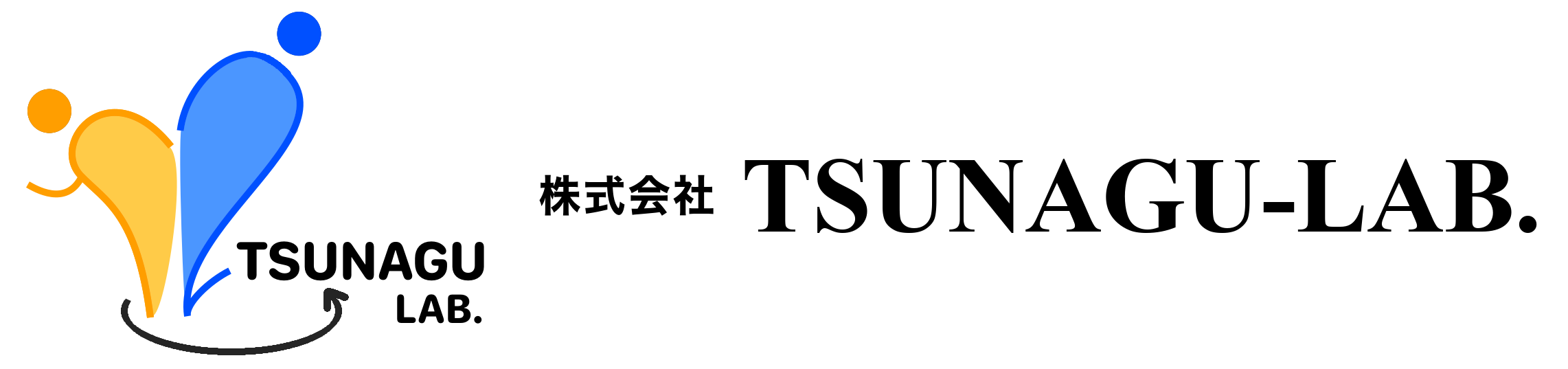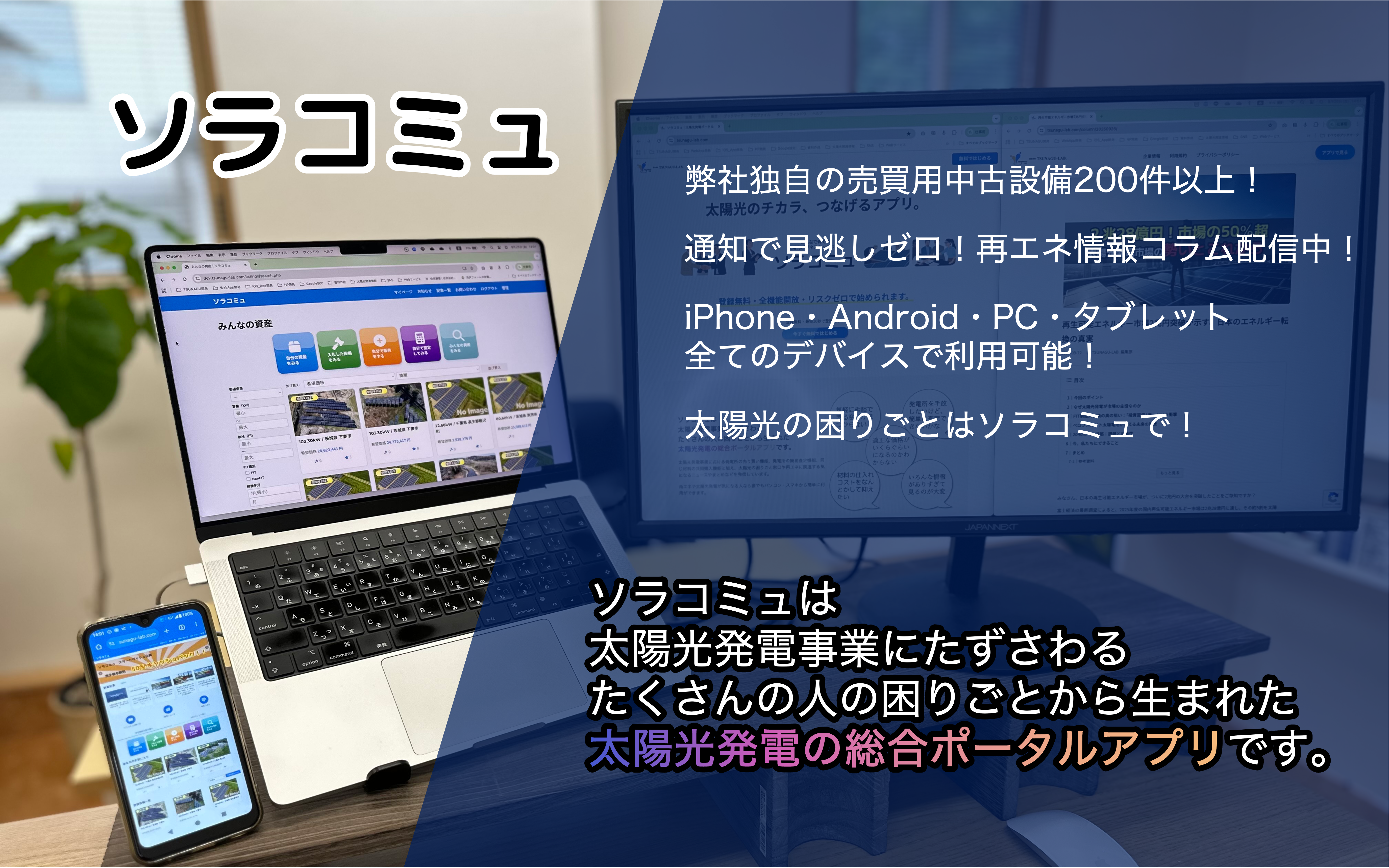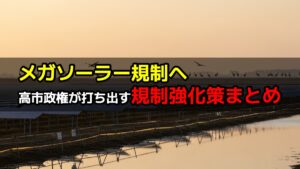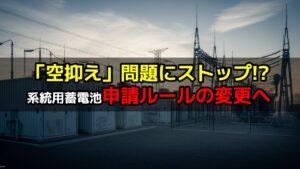みなさん、太陽光発電の売電価格の「値上げ」がまもなくスタートされることをご存知ですか?
2025年10月から始まる「初期投資支援スキーム」により、住宅用太陽光のFIT価格が15円から24円へ、事業用では11.5円から19円へと大幅に引き上げられます(出典:経済産業省 2025年3月21日発表)。
正直、最初にこのニュースを聞いた時、「え?また補助金バラマキ?」と思った方も多いのではないでしょうか。
でも、今回の制度改革は、これまでのFIT制度とは根本的に違うんです。
売電価格「引き上げ」の衝撃:13年ぶりの方向転換が意味するもの
FIT制度が2012年にスタートして以来、売電価格は一貫して下落の一途をたどってきました。事業用太陽光の買取価格は、制度開始時の40円/kWhから2025年度には11.5円/kWhまで、実に71%も下落しています。
これは太陽光パネルの価格低下と技術進歩を反映した「当然の流れ」として、業界も受け入れてきました。
ところが、2025年10月から導入される初期投資支援スキームは、この13年間の流れを180度転換させる画期的な制度変更なんです。
なぜ今、価格を上げるのか?
経済産業省の調達価格等算定委員会の資料によると、2024年10月のアンケートで、太陽光発電の設置を検討している企業の79%が「投資回収年数の長さが導入の障壁」と回答しています。
つまり、FIT価格の下落により、初期投資の回収に10年以上かかるケースが増え、多くの企業や個人が太陽光発電の導入を躊躇している実態が明らかになったのです。
ここに、日本のエネルギー政策の大きなジレンマがありました。
2段階価格の巧妙な設計:国民負担を増やさない「魔法」の仕組み
初期投資支援スキームの最大の特徴は、買取期間を前期と後期に分ける「2段階価格設定」です。
住宅用太陽光(10kW未満)の場合:
- 1〜4年目:24円/kWh(現行の1.6倍)
- 5〜10年目:8.3円/kWh(現行の約半分)
事業用太陽光(屋根設置)の場合:
- 1〜5年目:19円/kWh(現行の1.65倍)
- 6〜20年目:8.3円/kWh(現行の約72%)
でも、これって結局国民負担が増えるんじゃないの?
ここが今回の制度設計の巧妙なところです。
経済産業省の試算によると、この2段階価格を適用しても、割引現在価値ベース(割引率2%)で計算すると、従来の固定価格による国民負担と同等以下になるよう設計されています。
なぜそんなことが可能なのか?
答えは「時間価値」にあります。
初期に高い価格を設定することで、設置者は早期に投資を回収できます。一方、後期の価格を市場価格(8.3円/kWh)程度に抑えることで、長期的な国民負担の増加を防いでいるのです。
屋根設置にこだわる理由:出力制御問題との闘い
2025年度、九州電力管内では年間50回以上、最大で36%もの太陽光発電が出力制御(発電停止)される見込みです。全国で約20億kWhの再エネ電力が無駄になっている現実があります。
なぜこんなことが起きているのか?
春や秋の電力需要が少ない時期に、大規模太陽光発電所から大量の電力が供給されると、電力系統が不安定になるため、やむを得ず発電を停止させているのです。
屋根設置型が解決の鍵となる3つの理由
1. 自家消費による系統負荷の軽減 屋根に設置された太陽光は、その建物で消費されるため、電力系統への負荷が小さくなります。
2. 分散型電源としての安定性 大規模発電所と違い、小規模な発電設備が広く分散することで、系統への影響を分散できます。
3. 地産地消によるエネルギーロスの削減 発電場所と消費場所が近いため、送電ロスが最小限に抑えられます。
見落とされがちな視点:PPAビジネスへの影響
初期投資支援スキームの導入は、実はPPA(電力購入契約)ビジネスにも大きな影響を与える可能性があります。
太陽光発電業界団体は「住宅用PPAモデルの融資確保のため、10年間の買取期間が必要」という要望書を提出しています。なぜなら、後期の低価格(8.3円/kWh)では、PPAモデルの収益性が確保できない可能性があるからです。
これに対し、調達価格等算定委員会のある委員は「本来はFIT/FIPが終結したあとに様々な創意工夫が生まれて然るべきなのに、情けない団体だと思われても仕方ない」と厳しい指摘をしています。
ここに、日本の再エネ産業の構造的な課題が浮き彫りになっています。
2040年への道筋:残された時間は15年
第7次エネルギー基本計画では、2040年度の電源構成における太陽光発電の比率を22〜29%に引き上げる目標が掲げられています。これは現在の約3倍の導入量が必要ということです。
達成への3つのシナリオ
シナリオ1:屋根設置の爆発的普及 初期投資支援スキームにより、これまで導入を躊躇していた層が一気に動き出す可能性があります。特に、新築住宅の太陽光設置率は現在31.4%ですが、2030年度には60%を目指しています。
シナリオ2:ペロブスカイト太陽電池の実用化 2025年、積水化学工業がついに事業化を発表したペロブスカイト太陽電池。軽量・柔軟な特性により、従来設置が困難だった壁面や工場屋根への設置が可能になります。
シナリオ3:蓄電池との組み合わせによる出力制御対策 FIP制度への移行と蓄電池の導入により、出力制御を回避しながら収益性を確保する新たなビジネスモデルが生まれる可能性があります。
今すぐ動くべきか、様子を見るべきか?
2025年10月を待つべき3つの理由
- 投資回収期間が大幅に短縮 初期4〜5年間の高価格により、投資回収が3〜4年短縮される見込み
- 補助金との併用が可能 ストレージパリティ補助金など、各種補助金との併用により更なるコスト削減が期待できる
- 新築・既築を問わず対象 現時点では新築建物も支援対象に含まれる方向で検討されている
一方で、注意すべきポイント
- 申請が殺到する可能性があり、工事業者の確保が困難になるかもしれない
- 後期の低価格期間での収益性を慎重に検討する必要がある
- 出力制御リスクは依然として存在する(特に九州・中国・四国エリア)
まとめ:エネルギー転換の「最後のチャンス」
初期投資支援スキームは、単なる価格調整ではありません。
これは、日本が2040年の再エネ目標を達成するための「最後の切り札」とも言える政策転換です。
13年間続いた価格下落トレンドを反転させるという大胆な決断の背景には、「このままでは目標達成が不可能」という強い危機感があります。
しかし、ここで重要なのは、この制度が「持続可能」かどうかです。
国民負担を増やさずに普及を加速させるという、一見矛盾する目標を達成できるかは、まだ未知数です。制度開始後の導入実績と出力制御の状況を注視しながら、必要に応じて軌道修正していく柔軟性が求められるでしょう。
太陽光発電の導入を検討している方は、2025年10月という節目を意識しながら、自身の状況に合わせた最適なタイミングを見極めることが重要です。
日本のエネルギー転換は、今まさに歴史的な転換点を迎えています。
参考資料
- 経済産業省「再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格等と2025年度の賦課金単価を設定します」(2025年3月21日)
- 経済産業省 調達価格等算定委員会「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」(2025年1月30日)
- 資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御に関する短期見通し等について」(2025年1月23日)
- 経済産業省「初期投資支援スキームについて」第102回調達価格等算定委員会資料(2025年1月30日)
- 環境ビジネスオンライン「屋根置き太陽光への初期投資支援スキーム、経産省が具体案を提示」(2024年12月17日)
※この記事はWriters-hub様のご協力によりAIで生成・編集した記事を元に作成しました。
記事内容の詳細については参考資料をご覧ください。